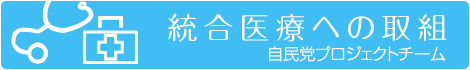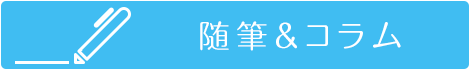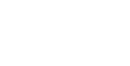五輪を「支える」磨け
朝刊 2014/04/08 スポートピア
3月26日、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の理事会メンバーが一同に会した。私は改めてスタートラインの重みをかみしめる気分だった。
05年から招致活動に携わってきたが、昨年9月、プエノスアイレスの地で感激に浸ることができたのは、ほんの5分間ほどだった。沸き立つ歓喜の後、「あと7年足らずで全て準備しないといけない」という責任感で胸が締め付けられるように痛くなった。
私の生年月日は1964年10月5日。そう、東京五輪開会式の5日前に生まれた。聖子という名は、北海道から開会式に駆け付けて生で聖火を見て感動した父が、「オリンピック選手にしたい」という願いを込めてつけてくれた。父の口癖を子守唄のように聞かされて育ったので、生後5日目からイメージトレーニングを施されてきたようなものかもしれない。
私の中で五輪の輪郭が鮮明になったのは、72年に札幌で開かれた冬季五輪だ。笠谷幸生さん、金野昭次さん、青池清二さんがスキージャンプ70m級(現ノーマルヒル)で金、銀、銅と3つのメダルを獲得し、国旗掲揚台を日の丸が独占した。
テレビでその光景を見たとき、子どもながらに「これがオリンピックなんだ!」とすっかり理解した気になってしまった。それまでは意味もわからないままに父との合言葉だった、「オリンピック」が自分の目指すものとして明快に脳内にインプットされたのだ。
得意とするスケートが五輪種目であることも知り、生意気にも「スケート選手になって出る」と決意した。当時、小学校2年生だったが、その瞬間のときめきは今も鮮明に覚えている。以来、オリンピックに魅せられ、心技体を鍛え、魂を磨くことに心血を注いできた人生となった。
先輩オリンピアンの雄姿に刺激を受けたことですべてが始まった。その経験があるからこそ、20年五輪の成功は日本選手団の活躍にかかっているという重みを肌感覚で理解できる。現在、日本オリンピック委員会(JOC)をはじめ、スケートや自転車の競技団体で強化や育成に取組み、国にも強化支援の拡充をお願いしている。
もっとも、五輪の感動は、子供たちにオリンピアンという夢を与えることにとどまらない。スポーツは「見る、する、支える」の三つの好循環が理想である。
「支えるスポーツ」というと指導者やスポンサーを連想されるかもしれないが、ホスト国という機会はボランティアの養成などを通じて「支える」を成熟させる好機になる。この好循環が成立して初めて、スポーツの安定的発展も望める。 より多くの人々にオリンピズムを浸透させ、それぞれが参加者である意識を持ってもらえる6年間にしたいと思う。
(日本スケート連盟会長)