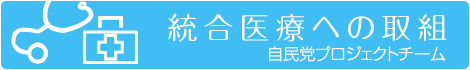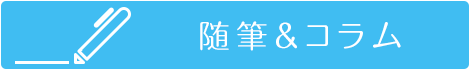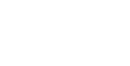夢の舞台 オリンピック!
運命の不思議さ

1念願のオリンピック初出場を果たしたのは、第14回冬期オリンピック・サラエボ(ユーゴスラビア)大会で、19歳の時でした。
物ごころつく前から、ずっと父に聞かされてきた聖火のすばらしさ・・・。点火の瞬間、聖火は神が放った光の矢のようなに見えました。その感動は、とても一言では表現できません。全身を稲妻のような衝撃が駆け抜け、涙をこらえるのに大変でした。
もし「聖子」という名前でなければ、ここに立つことは決してなかったでしょう。こんなことが現実ににあるのかという不思議な気持ちになりました。また人をこんなに感動させるオリンピックのすばらしさや、夢を託してくれた父の気持ちの深い部分が改めてわかった気がして、うれしさと同時に、責任の重さも感じました。
果たして、私はこの舞台に立つのにふさわしい人間なのか。この素晴らしい聖火に恥じないような人間になりたいと強く願い、そのためにはどんな時も納得のできるレースをしようと決意しました。
オリンピックの真の意味とは
サラエボ五輪は、冬期オリンピック史上初めて社会主義国で開催された大会です。またサラエボは、多くの民族や宗教が複雑にからみ合った難しい地域であり、ユーゴスラビアという国も、今はもうありません。
学校の教科書で社会主義国というものを習っていても、実際にその国に行って感じたショックは大きいものでした。そのころのサラエボは平和ではありましたが、日本の中古車を使ったタクシーが、割れた窓に新聞紙を貼って走っていたり、前年の世界ジュニア選手権で訪れた時に比べ、外貨獲得を狙って物価が急上昇していたりしました。
高度経済成長を遂げた日本で育った私には、生活の多くが貧しくも不便に感じられました。しかし、そこにはボランティアでオリンピック開催を支えてくれる大勢の人がいて、その笑顔の優しさは今でも忘れられません。
さまざまな主義・主張や宗教、それぞれの国の事情を抱えた世界中の人達が、スポーツを通じて一体になり、理解しあい、世界平和を望むことの素晴らしさを改めて感じました。
子供の頃、単純に「世界最高の運動会」と考えていましたが、現実のオリンピックは大きく異なっていて、その大きさと重みを全身で感じ取ったサラエボ五輪でした。
新たな挑戦と「感動をありがとう」

19歳から31歳までの12年間で、私は冬のスケート4回、夏の自転車3回の計7回、オリンピックに出場しました。
1984年冬サラエボ、1988年冬カルガリー/夏ソウル、1992年冬アルベールビル/夏バルセロナ、1994年冬リレハンメル、1996年夏アトランタです。どの大会もそれぞれ貴重な体験であり、とても思い出深いものです。
常に心がけていたのは、最大限の努力をし、聖火に恥じないレースをしようということだけでした。156センチの体格や肺活量の少なさなど、スポーツ選手としてのハンディは、やり過ぎと言われる程の練習量でカバーしました。おかげでサラエボの次のカルガリー五輪では、スピードスケート5種目すべてに日本新記録で入賞することができました。しかし、最後の種目5000メートルは、力を使いきり、転倒してのゴールインでした。
多くの方に「メダル以上だった」「感動をありがとう」という言葉をいただきましたが、選手としては、最後のレースまでしっかり滑りきる体力が無かったということです。
メダルで感動してもらえるようでなければと、唇を噛んだ悔しさが、次のオリンピックに向かう力になりました。
もっと強い自分になるために

カルガリーが終わると、私は自転車競技の選手として、その夏のソウル五輪を目指しました。日本での前例がなかったために、当時はずいぶん騒がれたものです。
もともとスピードスケートと自転車は使う筋肉が似ているため、スケート選手は夏のトレーニングメニューに必ず自転車を取り入れます。また、世界的には、スケートのチャンピオンが自転車に転向したり、夏冬両方で活躍したりといったことは、珍しくありませんでした。私も挑戦してみたいという気持ちは、サラエボ以前からのものでした。
スケート界しか知らなかった私が新しい環境に入り、短期間で競技の方法を覚えるのはとても大変でした。夏冬を目指すことで体を休めるオフがなくなり、どちらもダメにしてしまう危険性もありました。
でも、そういう恐怖を乗り越えてこそ、強くなれるという信念がありました。メダル獲得は、ある意味で人間技を超えているように思いますが、人間力そのものの戦いです。
ダメになることを恐れていては、メダルには手が届かないような気がしました。今でも、その選択は間違っていなかったと思います。
メダル獲得を信じて
高校2年生で日本一になって以来、10年間タイトルを守り続けた結果、「橋本聖子は1番で当然」というイメージができてしまっていたのでしょうか。
アルベールビル五輪の前は、少し順位が下がっただけで「もうダメか?」と書き立てられ、選考成績のうえでも順当だった五輪代表の内定を疑問視する声さえ出てしまいました。ひざの故障その他の不調に悩まされていた私は、いくつかの大会では無理をせず、オリンピックだけに照準を合わせた調整を組み立てていたのです。
そして、シーズン前のケガによる練習不足を解消するために1ヵ月前から単身オーストリアに行き、毎日40〜50キロメートルの滑り込みをして、一から筋肉を作り直しました。「当日は最高の状態で迎えられる」と、毎日理想の滑りをイメージしました。イメージトレーニングでは、氷の状態、フォーム、インかアウトか、組む選手との駆け引き、あのコーナーでコーチがラップをこう告げるといったことまで、すべてをビデオ画像のように頭に描きます。そして、例えば1000メートルで1分20秒を狙うなら、イメージの中でフィニッシュした時、ストップウォッチが1分20秒を表示しているところまで頭脳に叩き込むのです。
こうして、アルベールビル五輪の1500メートルで、私はついに銅メダルを獲得しました。「冬期五輪史上初の日本女子選手の快挙」と、多くの方々に喜んでいただくことができました。
負けても、相手を称賛できるということ

オリンピックを通して、とても親しくなれたのは、不思議と自分と同じような位置で常に勝ったり負けたりを繰り返すライバルと呼ばれるような間柄の選手達でした。
他の選手も同じでしょうが、私はいつも心からライバルの応援をしていました。自分の番が終わると、すぐに声援にまわって大声を出していました。
調子が悪い相手に勝ったところで仕方がない。お互いにいいレースをして、気持ちよく勝敗を分け合いたい・・・。
「努力に勝る天才なし」と父によく言われたものですが、努力だけでは成し得ない事も絶対にある、と私は思います。たとえ自分が大きな目標を達成できなかったとしても、その過程で精一杯の努力をしていれば、悔いも残らないし、それを達成した相手に、恨みや嫉妬を感じることもありません。そういう自分でありたいと、いつも考えていました。